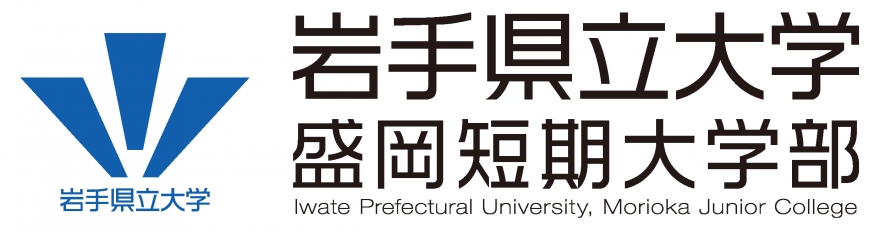基準9:社会連携・社会貢献
地域の復興支援活動とそれによる教育的効果
取組み事例
盛岡短期大学部発祥の、東日本大震災の災害復興支援として学生・教職員がペットボトル飲料水を手渡しで仮設住宅に届ける活動(通称「水ボラ」)を継続し、現在は海外大学の学生等や学外団体の外国人奨学生等が参加するなど、全学的な取り組みへと活動を広げている。この活動は学生が多文化共生について考える機会となっており、地域における喫緊の課題解決を支援することにとどまらず、教育的効果をもたらす取り組みとして発展していることは評価できる。
ここがポイント
- 災害復興支援として「水ボラ」を継続し、地域における課題解決を支援している。
- 現在は、海外大学の学生や学外団体の外国人奨学生が参加することによって、多文化共生について考え、教育的効果をもたらす取り組みとして発展している。
大学からのコメント
「水ボラ」は、東日本大震災復興支援活動の一環として、被災直後に岩手県に寄せられた支援物資の「ペットボトル飲料水」を、岩手県立大学盛岡短期大学部の教員が学生とともに仮設住宅等に配布したことに端を発するボランティア活動です。盛岡短期大学部が中心となり、飲料メーカーである(株)伊藤園の協力の下、東日本大震災津波の被災により仮設住宅又は災害公営住宅への転居を余儀なくされた地域住民に対し、世帯ごとに飲料水を配布することで会話のきっかけを作り、独居老人等への「声かけ」「見守り」を行うとともに、新たな地域コミュニティ形成の一助とすることを趣旨としています。岩手県陸前高田市を中心に毎月1回程度開催し、毎回10~30 人程度が参加しました。 こうしたボランティア活動に加えて、年1回「拡大水ボラ」として、米国オハイオ大学と共同で、愛知県中部大学留学中のオハイオ大学からの外国人留学生、飲料水及び寄付金の提供を受けている公益財団法人本庄国際奨学財団から、当該財団の奨学生である全国各地の大学院生、中部大学の日本人学生を加え、岩手県立大学でも全学的な取組へと活動を広げて、規模を拡大して実施しました。「拡大水ボラ」では、ペットボトル配布の他、大学間交流会をはじめとして、語り部による被災地学習、定住促進住宅、奇跡の一本松などの津波遺構見学、海岸清掃ボランティア活動などを実施しました。 新型コロナウイルス感染拡大による2年間の中断をはさんで、令和4(2022)年度からは、「被災地をフィールドとした防災学習及びボランティア活動を中心としたサービス・ラーニング」として位置付け、内容をボランティア活動中心から防災教育にシフトし、改めて関係大学及び財団との共同により、交流会はもとより、東日本大震災津波伝承館・津波遺構等の見学、避難所開設体験などを盛り込むなどして、復興防災学習プログラムとして実施しています。 こうした活動は、ボランティア活動体験にとどまらず、学生が多文化共生について考える機会ともなっており、教育的効果をもたらす取組として発展しているものととらえています。