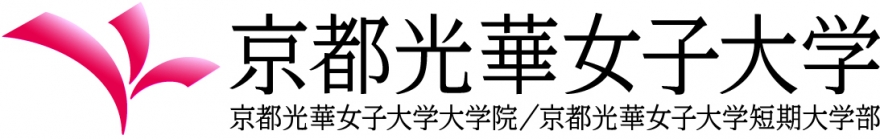基準7:学生支援
「学習ステーション」を中心とした多彩な学生支援
取組み事例
「学習ステーション」において、ピア・サポーターを募り、一部の必修科目と連動した授業外支援のほか、学生が企画した支援を通じて支援する学生と支援を受ける学生の双方の成長につながっている。また、近年では「学習ステーション」と「女性キャリア開発センター」等の諸組織との連携を開始し、学科・学年を超えて学生が関心のあるテーマについて少人数で自主的に学ぶグルー「学Booo(マナブー)」の実施や教職員が学生の学習状況を共有する「きずなネットワーク」の形成など、「エンロールメントマネジメント(EM)」の方針に沿った活動を発展させることで、早期に必要なサポートを行い、退学率の減少といった成果がみられることは評価できる。
ここがポイント
- 「学習ステーション」では、学生がピア・サポーターとして、教職員と連携して、学生の主体的な学びを支援している。
- 支援を受ける学生だけでなく、ピア・サポーター自身の学習の振り返りや、成長に貢献している。
- 「学習ステーション」と他の組織を連携し、学生支援の根幹である「エンロールメント・マネジメント」に沿った活動を発展させることで、退学防止等の成果をあげている。
大学からのコメント
本学では、学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるように学生支援のワンストップ化を目指し、各部署と学部・学科との支援ネットワークの強化、連携、情報共有を進めている。 特に本学が掲げる「エンロールメント・マネジメント(EM)」は、2008 年度文部科学省の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム」に選定された本学独自の学生支援体制であり、入学前から卒業後までの親身できめ細かい学生支援を徹底して行うことを目的としている。本学ではこのEMが学生支援の根幹を成しており、現在までこの取り組みを進化・発展させている。 学習支援において「学習ステーション」の位置づけは大きく、学部・学科の学生達がそれぞれの専門性を超えた形で学生間の支援を行うピア・サポーター制度が機能している点は本学の特色といえる。低学年からのサポート体制は、特に入学初期の学生にとっては見守られる安心感が学生の主体的な学びを促し、積極的な学習行動へと結びついている。また、教職員と連携したグループ学習などの取り組みも学習習慣の定着や成績の向上につながっていると同時に、学科や学年を超えたつながりやピア・サポーター自身の成長にもつながっている。 正課外活動を充実させる支援の一つとして「女性キャリア開発研究センター」が所管するラーニング・コミュニティ「学 Booo(マナブー)」がある。これは2010年度より開始した課外活動であり、同じ興味を持った学生が、学部・学科・学年の枠を超えて参加できる少人数で学ぶ自由参加型の学習グループである。教職員はアドバイザーであり、主体である学生が中心となって座学型、体験型、PBL(Project-Based Learning)型の活動を通して地域連携・社会貢献・産学連携活動への学びを深めている。一例として、「KOKA☆オレンジサポーターズ」では、高齢者や障がい者の「食べる機能の低下予防」とその支援方法について、近隣の高齢者・障がい者への啓蒙活動や、飲み込みやすい和菓子の開発に挑戦している。また、「酒づくりと人のつながり ~ 京都伏見の伝統文化を通じて~」では、京都伏見の酒蔵とコラボレーションし、酒造りの工程を体験しつつ、日本酒の魅力をPRするとともに、若い女性にも親しまれるオリジナル日本酒の企画・開発に挑戦している。