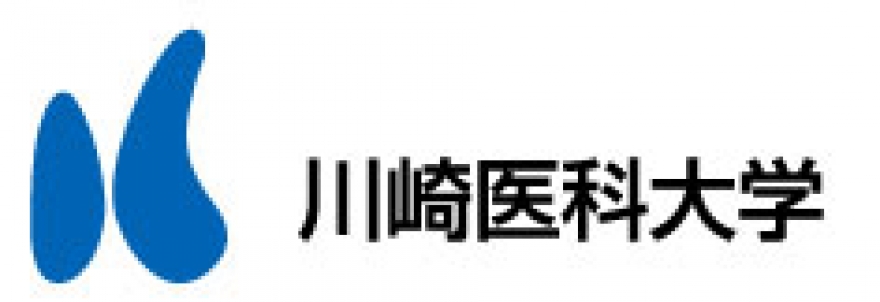基準8:教育研究等環境
多様な学生の能力伸長に資する教育研究等環境整備の取り組み
取組み事例
全学生を収容できる個別学習スペースとして学年別自修室を設け、5・6年次の学生には個別のブースを提供しているほか、学生寮の学習室や学生教職員ラウンジ、機能別研究の中心となる「中央研究センター」内に研究関連図書を配備したラウンジを設けるなど、学生の個人学習・グループ学習を促進する環境を整備している。さらに、「現代医学教育博物館」が有する多様な臓器標本を展示することに加え、臨床実習に活用しており、これらを通じて学生の能動的学習を支援し、学力のみならず多様な学生の能力伸長に有意な取り組みとして評価できる。
ここがポイント
- 多様な学生の能力を伸長する観点から、在学する学生の特性を踏まえて、学年別自修室をはじめとした、各種の教育研究等環境の整備を行っている。
- 「現代医学教育博物館」において、特色ある展示を行うとともに、臨床実習に活用することで、学生の能動的学習を支援している。
大学からのコメント
学生の個別自修をサポートする豊かな環境 1学年は全寮制で、良医にふさわしい人格を形成するための教育寮と位置付けられている。大学校舎棟に隣接した学生寮は、完全個室で学生自身のペースで学習が可能であるとともに、グループ学習が行える共用スペースも備えている。2学年以降は大学校舎棟内に学年別の自修室を設け、学生ごとの机を用意し、5,6学年には各机の間仕切りや本棚を設置し、落ち着いて学習ができるよう配慮している。また、自修室内の相談室、学生教職員ラウンジや附属図書館内のカンファレンス室など、グループ学習に適した環境を整えている。友人とのディスカッションによってコミュニケーション能力を涵養し、将来のチーム医療の実践や、良好な患者-医師関係の構築のきっかけとなることを期待している。 研究を活性化させるための交流スペース 本学では開学当初から、教員が研究活動を円滑に行えるよう研究を支援する「人・場所・機能」を集約し、教室ごとではなく、共通施設である研究センターを利用して研究を進めてきた。2015年には改組により5つの機能別ユニットからなる中央研究センターを発足させた。全ての教員が施設を利用でき、また、専任のオペレーターがサポートする体制としている。利用者同士の交流による研究の活性化を目指して2018年にKMSリサーチラウンジ(FUTAGO)を開設し、研究関連の図書も配架した。川崎医学会総会では近隣大学からの研究発表受け入れ、KMSメディカル・アークでは産学官マッチングの実施など、学外との連携にも注力している。 他に類を見ない現代医学教育博物館 創設者 川﨑祐宣が、開学時に海外の医学博物館を視察し、創立10周年記念として1981年に現代医学教育博物館を開設した。一般向けの健康教育博物館としてのフロアと、病理肉眼標本を主体とする医療者向けフロアがある。「百聞は一見に如かず」という当初の主旨を踏襲し、来館型の見学を継続するとともに、学校や公民館などへの出張展示、小中学生を対象としたかわさき夏の子ども体験教室などを行っている。学園内外の医学・医療系学生による見学も受け入れている。医学部学生に対しては、低学年での見学実習、臨床実習時の臓器観察に加えて、2学年の「医学研究への扉」における展示物作製や、メディカルイラストレーション実習など、希望する学生への教育も展開している。2022年度からは3Dプリンターを導入し、新たな教育資源の開発に取り組んでいる。