基準9:社会連携・社会貢献
学際的「奈良学」研究を中心とする多様な地域連携・地域貢献活動
取組み事例
「奈良」をフィールドに、帝塚山大学の知的リソースと地域のリソースを組み合わせた学際的な「奈良学」の多様な研究活動は、地域、産業界等をつなぎ、その連携を進化させる取り組みであり、学生参加型で実施することで、学生の主体的な学びの場にもなっている。そのほか、「プロジェクト型学習」による多様な地域連携活動や、「奈良学総合文化研究所」「考古学研究所」「心のケアセンター」「子育て支援センター」等における活動及び研究成果も地域社会に還元されており、今後も地域の拠点大学として活動を更に推進していくことが期待でき、評価できる。
ここがポイント
- 地域に根差し長年にわたり取り組み、文部科学省の私立大学研究ブランディング事業にも採択された「奈良学」研究を通じて、地域連携、産学連携を全学的に推進している。
- 「プロジェクト型学習」による地域連携活動が近年大幅に増加しており、学生の実践的な学びの場にもなっている。
- 「附属博物館」等の附置施設においてもさまざまな形で地域連携、地域貢献活動を続けており、今後も地域の拠点大学として活動を更に推進していくことが期待できる。
大学からのコメント
帝塚山大学が推進する「奈良学」は、本学を設置する学校法人が併置していた帝塚山短期大学(2000年度に本学組織に組み入れ)の名誉教授・青山茂氏が1980年代に提唱したものです。以来、全学的に「奈良学」研究を推進してきており、その実績は文部科学省の平成29(2017)年度私立大学研究ブランディング事業の採択にもつながりました。




本学は、このような「奈良学」研究をはじめとする研究成果の地域社会への還元を目的として、年間を通じて多くの公開講座を開催しており、たとえば「奈良学総合文化研究所」による公開講座「奈良学への招待」や、「考古学研究所」と「附属博物館」の共同開催による「市民大学講座」などがあげられます。2022年3月時点で開催回数が通算470回を超える「市民大学講座」は、2020年6月より過去に開催した講座の動画配信も行っており、オンライン上でいつでも視聴が可能となっています。公開講座以外にも、国家資格である公認心理師や臨床心理士養成のための学内実習機関ともなっている「心のケアセンター」による地域住民への心理相談活動や、「子育て支援センター」による「親子教室」、「つどいの広場」を通じた地域住民の子育て支援など、地域のニーズに対応した各種の支援を通じて地域の拠点大学としての役割を果たしています。
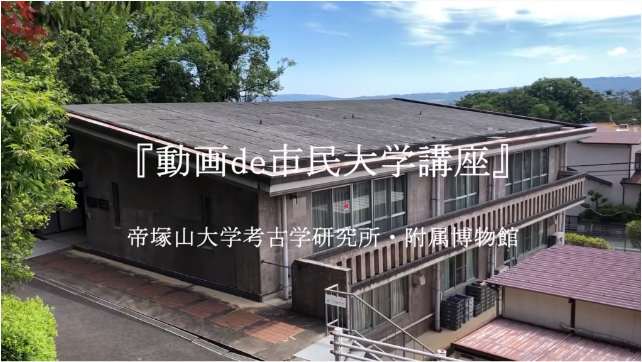


また、帝塚山大学は、かねてより「実学の帝塚山大学」を標榜し、学生たちの未来を見据え、人生を豊かにする力を身につける教育を展開しています。「実学の帝塚山大学」を実践する取り組みとして、行政や企業、地域とともに実社会の課題解決に取り組む「プロジェクト型学習」を重視しており、「プロジェクト型学習」などアクティブ・ラーニングの充実を図る施設の整備・拡充も行っています。2022年春には現代生活学部居住空間デザイン学科の実習施設として新たに『DESIGN Lab.』が誕生しました。
毎年開催している「『実学の帝塚山大学』実践学生発表祭~アクティブ・ラーニングの実践事例~」では、すべての学部・学科の学生代表がその成果を学内外に報告する機会を設けています。また、学生達が主体的に取り組むプロジェクト型学習、地域連携・産学官連携活動の成果は、『プロジェクト型学習実践事例集』としてまとめ、広く社会に発信するとともに、更なる活動の推進をめざしています。



.jpg)
関連サイト
- 研究・社会貢献https://www.tezukayama-u.ac.jp/social/
- 考古学研究所 ニュース『動画de市民大学講座』https://www.tezukayama-u.ac.jp/social/institute/arch/
- 「帝塚山プラットフォーム」の構築による学際的「奈良学」研究の推進https://www.tezukayama-u.ac.jp/tezukayama_platform/

