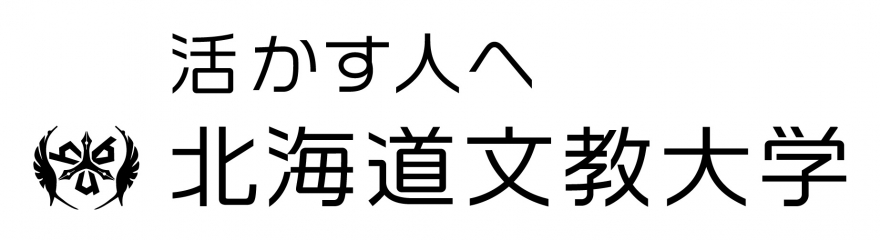基準9:社会連携・社会貢献
多様な地域連携と新たな産官学連携モデルの構築
取組み事例
「地域連携推進センター」を中心に、大学の所在地である恵庭市を拠点とした教育や食、福祉、医療、国際等の各学部の専門性を生かした多種多様な連携事業を展開し、食育の普及や子育て支援、障がい者の発達支援プロジェクト、地元企業と共同しての商品開発などに学生と教職員で取り組んでいる。これを発展させるべく、2023年度に「地域創造研究センター」を設置し、産官学の諸機関に所属する研究員で協働して地域の課題解決に取り組むなど、プラットフォーム形成の中核として地域と大学との新たな連携モデルを構築し、地域の知の拠点として機能することが期待できるため、社会連携・社会貢献に関する方針に基づく有意な取り組みとして評価できる。
ここがポイント
- 長期にわたって、専門性を生かした多様な地域連携事業を展開している。
- 産官学による新たな連携モデルの構築に繋がっている。
大学からのコメント
〇本学では、地域社会への貢献、地元企業等との連携を図ることを目的として、地域連携推進センターを中心に自治体をはじめ多くの企業・団体との連携協定締結を活発化させている。2024年度末で、自治体14件、民間企業53件、医療関係17件、教育関係23件、その他団体16件と合計123の包括連携協定を締結しており、本学の教育内容の特色を活かしながら、共同研究や共同事業、商品開発など様々な分野に展開し、連携事業数も年々着実に増加している。
特に、地元恵庭市との連携は、地域包括ケアシステムの進化・推進に向けた共同研究を行っているほか、不登校児童・生徒の学校復帰に向けた指導・支援を行う適応指導教室を「学びの森」として学内に設置している。
また、地域社会が抱える様々な課題の解決に向けて地域政策研究を行う、全国でも初めての私立大学と自治体との協働組織「地域創造研究センター」を設置し、地域への関心・理解を深め、より実践的な課題解決能力を身につけた人材の育成を目指している。
〇健康栄養学科の教員と学生が、様々な企業とのコラボにより商品やレシピの開発を行っており、その中には、健康の維持増進のみならずSDGsへの貢献をコンセプトに、食のバリアフリー、廃棄食材の利活用の問題解決に重点を置いたものもある。
また、食育活動の取組みも盛んに行っており、学生3名が食育アイドルプロジェクト「文教食ドル隊えにわっ娘.」を結成し、TwitterやYoutubeでの動画配信を中心に活動している。2つ目のアイドルグループ「IX-ALICE(イザリス)」も結成され、拒食症や孤食などをテーマに新たな活動を始め、2025年6月には、農林水産省が主催する第9回食育活動表彰で、この2つのグループが農林水産大臣賞を受賞することとなった。
〇障がい児(者)の発達支援の取組みである「北海道スマイルプロジェクト」や特別な支援を必要とする子ども向けの「チャレンジド教室」を開催しているほか、教員をめざす学生が教師になるための基礎を学ぶ、地元小中学校でのアシスタント・ティーチャーの取組みなど、積極的に地域社会と交流している。
〇こうした社会連携・社会貢献の取組みは、大学での研究の知見の還元はもとより、学生も社会との接点を持つことができ、地域での就職につながるなど、教育研究成果を着実に社会に還元するものとなっている。