基準4:教育課程・学習成果
「地域包括ケアセンター」と連携した実践的な多職種連携教育の推進
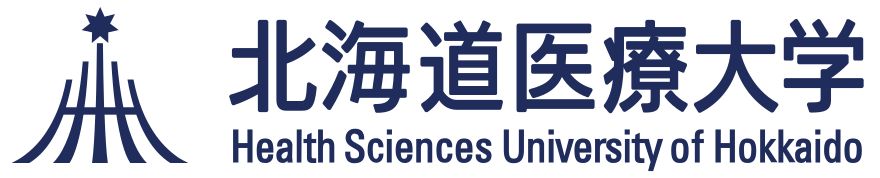
| 種別 | 大学評価 |
|---|---|
| 年度 | 2024年度 |
| 区分 | 私立 |
| 規模(収容定員) | ~4,000人 |
| 関連タグ |
取組み事例
全学部・学科を横断した必修科目「多職種連携入門」に加え、高学年に「全学連携地域包括ケア実践演習」を新たに配置し、大学が所在している自治体の地域包括ケアシステムの一環にある附属施設「地域包括ケアセンター」の利用者を訪問して学生が在宅医療を実践的に学ぶとともに、利用者の声を通じて生活や人生等の質を考える機会となっている。医療系総合大学の資源を生かして地域における医療の課題を体験し、学生が同じ課題に対してそれぞれの専門性に基づくケアを検討・提案することで専門性を超えて視野を広げるとともに、現代社会で求められている多職種連携を推進する人材育成につなげることが期待できることから、効果的な教育として評価できる。
ここがポイント
- 「全学連携地域包括ケア実践演習」では、「地域包括ケアセンター」の利用者を訪問して学生が在宅医療を実践的に学び、利用者の声を通じて生活や人生等の質を考える機会となっている。
- 医療系総合大学の資源を生かして、それぞれの専門性に基づくケアを検討・提案することで専門性を超えて視野を広げるとともに、現代社会で求められている多職種連携を推進する人材育成につなげることが期待できる。
大学からのコメント
現代社会における保健・医療・福祉では、個体差に基づく個々人に最も適したケア、及び個人の人格を尊重し、個々人を最も幸福にするケアが求められている。また、高度に専門化・複雑化した保健・医療・福祉システムや少子高齢化時代の中においては、一人の専門家がその知識や能力を駆使して、単独で課題を解決するということは不可能であり、より質の高いケアを提供するために専門職業人が互いに協働する「多職種連携」が重要である。本学はこのニーズに応えるべく、6学部9学科および歯学部附属歯科衛生士専門学校を擁する医療系総合大学の強みを活かし、学部・学科の枠を越えた多職種連携教育を体系的に展開している。
2014(平成26)年度から「多職種連携入門」を、2020(令和2)年度からは「全学連携地域包括ケア実践演習」を開講している。「多職種連携入門」(必修:2単位)は、第1学年を対象に多職種連携の理念と方法およびその具体的実践と課題について学ぶ。具体的には、学部・学科を越えたグループ構成で座学及びグループディスカッションを含む演習を経験し、多職種連携協働(IPW:Interprofessional working)における態度、知識、技能の獲得を目指すこととしている。「全学連携地域包括ケア実践演習」(選択:2単位)では各学部・学科の高学年の学生(3~5年)を複数の学部・学科混合グループに分け、地域包括ケアにおける専門職の役割や多職種連携のあり方を学ぶ。具体的には、本学の附属施設「地域包括ケアセンター」の専門職と利用者・家族の協力を得て、①多職種連携による対象者理解の観点に注目しながら、専門職の活動を同行訪問もしくはオンラインで見学する。②対象者理解を深めるために専門職、対象者・家族にインタビューする。③多職種で連携して対象者の全体像をとらえる。④得られた情報をもとに自分の専攻とは異なる学科の学生とともにディスカッションを行い、地域包括ケアにおける多職種連携のあり方に関する考えをまとめている。この演習は、対象者や家族の暮らしに触れ、支援を提供している専門職の活動をリアルに学ぶことができる貴重な機会となっている。また、演習前と演習後にPROGテストを実施し、学修効果の検証を行っている。
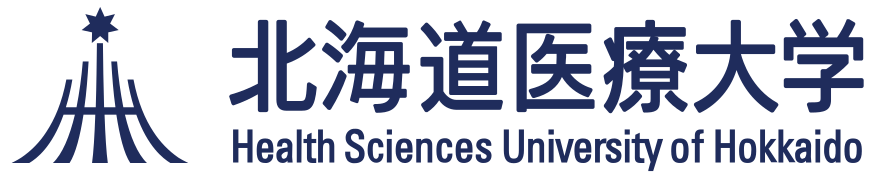
関連サイトのURL
- 北海道医療大学 受験生応援ページ「多職種連携」
- https://manavi.hoku-iryo-u.ac.jp/inter-professional/
