基準4:教育課程・学習成果
ICTを活用した学生の学びの活性化とその学びの成果を可視化する取り組み
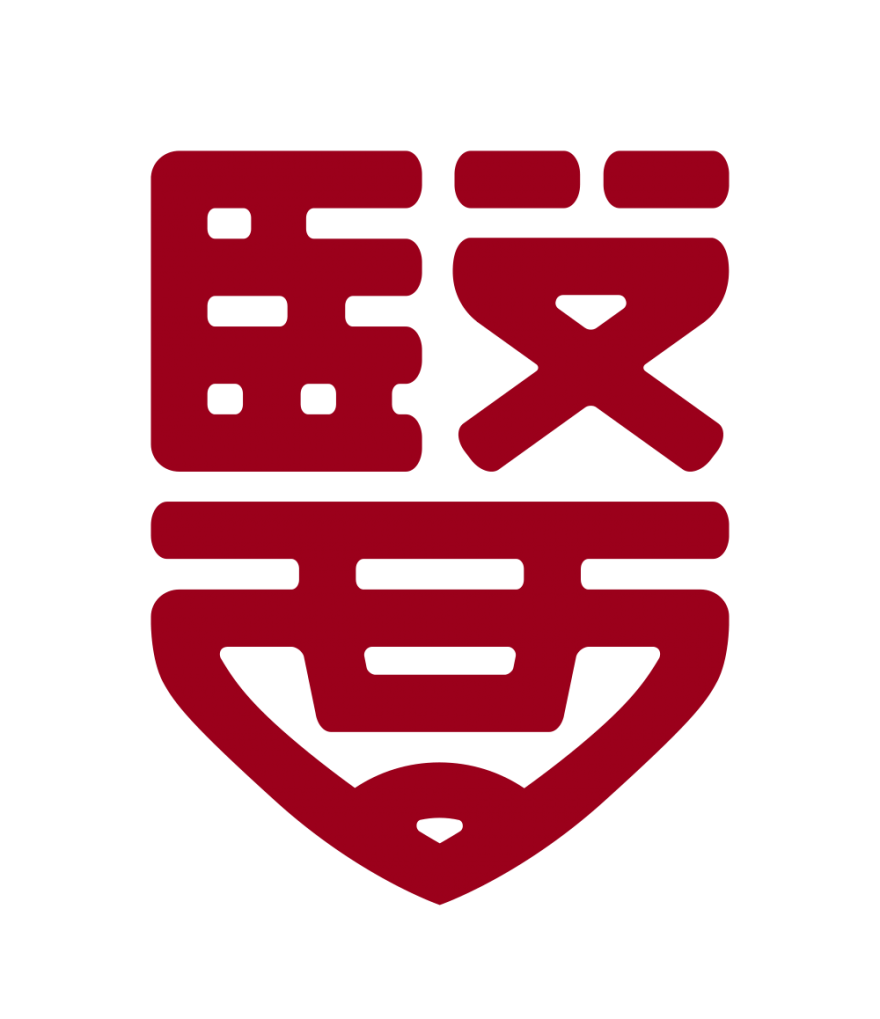
| 種別 | 大学評価 |
|---|---|
| 年度 | 2024年度 |
| 区分 | 私立 |
| 規模(収容定員) | ~4,000人 |
| 関連タグ |
取組み事例
学習支援システムである「e自主自学」では、授業中のクリッカー、講義課題等の提出、授業に関する確認テスト等を通じて、オンライン上で教員と学生又は学生同士の双方向のやり取りを可能にすることで、学生の自学自習のみならず、学生同士が相互に学習状況を把握するためのツールとしても活用している。また、学位授与方針に基づく「教育到達目標」のアンケート調査結果をレーダーチャートとして可視化し、学生自身が到達度を把握できるようにすることに加えて、学習実践記録として「eポートフォリオ」を活用することにより、学習履歴・実習評価を記録・蓄積し、教員によるフィードバックを踏まえることで学習成果を適切に把握できるように整備している。これらを通じて、学生が自らの学びの成果を振り返ることができるようにするなど、ICTを活用して学生の学習を活性化するとともに、多角的な学習成果の測定に取り組んでいることは評価できる。
ここがポイント
- 「e自主自学」は、オンライン上で教員と学生又は学生同士の双方向のやり取りを可能にすることで、学生の自学自習のみならず、学生同士が相互に学習状況を把握するためのツールとしても活用している。
- 学習成果をレーダーチャートとして可視化し、学生自身が到達度を把握できるようにしている。
- 「e自主自学」内の「eポートフォリオ」は、学習履歴・実習評価を記録・蓄積し、教員によるフィードバックを踏まえることで客観的な学習成果を適切に把握できるように整備している。
大学からのコメント
本学では、学修成果を多角的な指標で評価することを試みています。例えば、医学科では、卒業時の学修成果の定量化を目的として、①国家試験の成績、②OSCE(実技試験)の成績、③卒業到達目標の自己評価、④卒業到達目標に連関させたアセスメントテスト、⑤臨床実習の評価、⑥卒業後臨床研修開始時の能力評価の6種類の指標を活用し、学修成果の可視化に努めています。これらの指標は、カリキュラムと評価方法の点検・改善に役立てられています。
さらに、可視化された学修成果は学修を促進するための指標としても活用されています。学生が期待される学修成果のレベルと現状の乖離を認識し、学修を促進できるように、ラーニング・マネジメント・システム「e自主自学」を活用したフィードバックを積極的に行っています。
例えば、到達目標の達成度は、学年平均と比較したレーダーチャートで示し、「e自主自学」で参照できるように設計しています。また、人間学系の科目の課題、臨床実習中の日誌、臨床実習で経験した症例・手技はeポートフォリオに蓄積し、教員からのフィードバックを踏まえながら、学修の過程や到達度の乖離を振り返ることができる環境を整備しています。
今後も、ICTを活用して学修成果を明確に可視化し、学生の主体的な学修へとつなげる体制の構築に取り組んでまいります。
