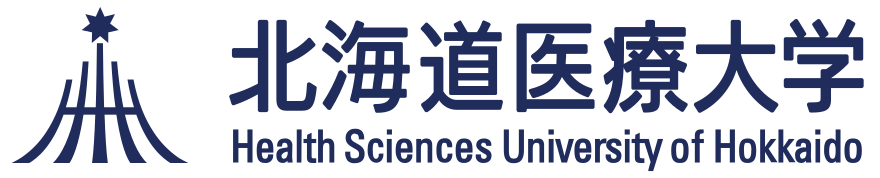2 教育の内容・方法・成果
学習効果の向上を図るための電子ポートフォリオ・リンクノートの活用
取組み事例
電子ポートフォリオを利用した教育の充実を図っているほか、リンクノートを活用して臨床実習における知識の評価を行うなど、手厚い教育体制を保持していることは、学生の知識の整理にもつながり、長所として評価できる(評価の視点2-12)。
ここがポイント
- 電子ポートフォリオを用いて学生による振り返りを行っている。
- リンクノートを活用し、教員が知識を評価している。
大学からのコメント
本学の診療参加型臨床実習では歯学教育モデル・コア・カリキュラムに記載されている水準(水準Ⅰ〜Ⅳに分類して示されている各診療行為を本稿では「水準」として記載する)を実施する際に患者との間に信頼関係が存在することを重視し、一人の臨床実習生(Student Dentist:以下SD)が同じ担当患者を継続して診療するよう指導している。自験の評価にあたっては、行った治療の種類と学生がどこまで自験ができたかを評価し、学生に対してフィードバックを行う必要があるが、レポートや口頭試問などのためにSDは指導医を長時間待たなければならないことが多かった。このため症例数の計算と文章によるフィードバックを同時に行うことができる電子ポートフォリオを開発した。SDは診療後に電子ポートフォリオに必要事項を入力し指導医に送信する。それを受け取った指導医は術式の添削や疑問点や反省点に対するフィードバックを行うとともに、G領域や水準の評価を行う。G領域の評価項目はPost-CC PXの臨床能力試験(CPX)の評価項目と一致させており、1度の診療ですべての評価項目がB評価以上(概ね自験できた)であった場合を1症例完了としてカウントし、全診療科をあわせた合計症例数を到達目標として設定している。一方、水準の評価項目は処置ベースとしているため、各診療科で最低限必要とされる到達目標を設定している。
また学生間で担当症例が異なることによる知識のばらつきを避けるため、過去の歯科医師国家試験をベースとしたリンクノートを提供し、1日1枚のペースでSDが回答を作成したものを指導医が添削して知識の整理を行っている。さらに、臨床推論の教材を作成し医療面接や診察により患者の症候・病態から疾患を診断し治療方針を導き出す臨床推論能力の向上を目指している。
電子ポートフォリオは歯科医師臨床研修でも用いられており、学部から臨床研修へのシームレスな移行に役立っている。歯科医師臨床研修で用いていたDebutでは症例数をカウントすることはできたが、診療内容のフィードバックはできなかったため、電子ポートフォリオの導入で効率的な指導が可能となった。またリンクノートについては多職種連携教育でも活用できるため、学部や分野間の学際的な学修に導入することを予定している。
関連サイトのURL
- 北海道医療大学 歯学部
- https://www.hoku-iryo-u.ac.jp/dent/