基準2: 内部質保証
大学ビジョン実現に向けた部局横断型内部質保証システム
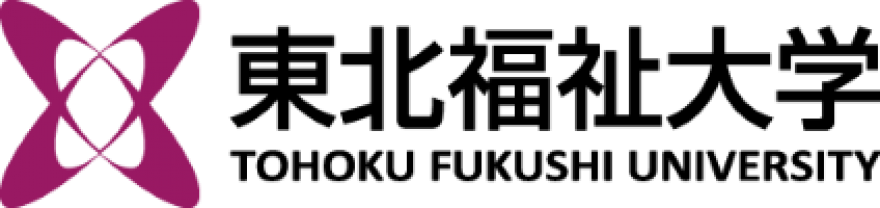
| 種別 | 大学評価 |
|---|---|
| 年度 | 2023年度 |
| 区分 | 私立 |
| 規模(収容定員) | 4,001人~8,000人 |
| 関連タグ |
取組み事例
全学的な内部質保証の推進組織である「内部質保証委員会」のもとに、「内部質保証小委員会」を各学部、研究科及び事務部門に設け、各小委員会においては各部局の点検・評価結果の共有のみならず、事例の照会や改善に向けた助言を相互に行うなど、多角的な視点での自己改善に取り組んでいる。そのうえで、「内部質保証委員会」が大学ビジョンや事業計画等を踏まえた全学的な観点からの評価及びマネジメントを行う内部質保証体制を構築している。このように各小委員会において、改善につながる情報を交換・共有する取り組みが部局相互で活発に行われており、これと「内部質保証委員会」の改善指示によって、多くの特色ある教育の創出につながっていることは評価できる。
ここがポイント
- 「内部質保証委員会」が付す全学的な観点からの改善指示を、各部局がそれぞれの目標として反映し、指示の内容に応じて積極的に部局間連携を図っている。
- 各学部等に設置の「内部質保証小委員会」では、各部局の点検・評価内容の情報共有だけでなく、事例の照会及びアドバイスを行うなど、部局横断的な点検・評価及び改善に取り組んでいる。
- 内部質保証活動によって、多職種連携教育やデータ・サイエンス教育の拡大など、大学ビジョン実現に向けた多くの成果が生み出されている。
大学からのコメント
【内部質保証のあゆみ】
本学の内部質保証は、自己点検・評価の実施を努力義務とすることが大学設置基準に明記された1991年に「自己評価委員会」を設置したことから始まり、2000年には「大学院自己評価委員会」と「教育業績評価委員会」を設置し、これを受けて 2001年に「FD委員会」を設置。恒常的に教員の研究および教育業績の提出を求め、『教育・研究業績書』として刊行し内外に配布することを、自己点検・評価の活動の一部としていました。また、2003年度に本協会の加盟判定審査の際に作成した『自己点検・評価報告書』を刊行し、学内外に発信してきました。以降も内部質保証の質的向上を目標として自己点検・評価活動を実施してきました。年度ごとの点検評価をまとめた「自己点検・評価報告書」も毎年作成し現在に至ります。
【内部質保証システム】
本学では、各部門(各研究科、各学科、各事務部門)のすべてにおいて、本学独自の様式である「内部質保証自己点検・評価シート【様式1】」において、毎年、①年度当初における現状と課題、事業計画に照らした目標立案、②中間評価(現状報告)、そして③最終評価(自己評価、効果を上げた事項・発展方策・課題改善事項等)を記載します。
目標設定時には、前年度の「自己点検・評価報告書」に記載の課題や各部門から提出された最終評価【様式1】をもとにした内部質保証委員会からの助言「評価結果報告書【様式2】」を漏れなく反映することを義務付け、最終評価時には学生アンケートや客観的データの基づく検証結果の記載を必須としています。
【内部質保証小委員会】
各部門の自己点検・評価結果は、各学部(4小委員会)、各研究科(2小委員会)、事務部署(全部署合同で1小委員会)ごとに設置された7つの「内部質保証小委員会」で確認・審議の後、大学レベルである内部質保証委員会に諮られます。そのうえで内部質保証委員会では、各部門より提出のあった様式1をもとに長所や改善点の指摘を行い、各部門は、年度後半に次年度の事業計画や目標に設定し実行します。この一連のプロセスをPDCAサイクルの1クールとしています。
【自己点検・評価と各種方針・事業計画等との関係】
様式1に記載の目標は、建学の精神や教育の方針はもとより、3ポリシーや各種方針、中期事業計画、年度事業計画などに基づき設定されます。したがって、様式1に記載の内容はこれから各種方針、事業報告、点検・評価報告書の原資となり得ます。
