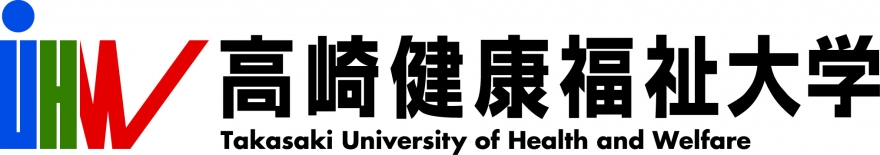基準9:社会連携・社会貢献
学問の深化や市民意識の醸成等を展開する「子ども・家族支援センター」の取り組み
取組み事例
「ボランティア・市民活動支援センター」が地域との連携の窓口となって収集した地域課題への解決に教育と連動して取り組んでおり、なかでも「子ども・家族支援センター」では、子どもと家族の心と体の問題に向けて医師・看護師・臨床心理士・保育士等の専門家による相談体制を設け、「親子ふれあい教室」を子ども教育学科等の学生の学びと連携して運営し、障がいのある子どもを受け入れるなど福祉の面で先進的な取り組みも見られる。このようにボランティア活動のみならず、学生が実社会と接することによって学問の深化や市民意識の醸成、他者への理解を図る活動を展開していることは、建学の精神である「自利利他」を実現する取り組みとして評価できる。
ここがポイント
- 子どもと家族の心と体の問題に向けて医師・看護師・臨床心理士・保育士等の専門家による相談体制を設けている。
- 障がいのある子どもを受け入れるなど福祉の面で先進的な取り組みを行っている。
- 学生が実社会と接することによって学問の深化や市民意識の醸成、他者への理解を図る活動を展開している。
大学からのコメント
子ども・家族支援センターは学生の学びの場ともなっており、子ども教育学科 3年生の「保育方法論」の授業において、学生が親子の関わりに直に触れ、子育て支援を体験できる環境を提供している。子育ての経験のない大学生が、机上で学んだ保育や託児を実際に体験し、子育て中の母親と関わることによって、自発的に家族支援に関する問題を発見する実践的機会となっている。子ども・家族支援センターでの体験は、保育士・幼稚園教諭を目指す学生の教育活動の推進に重要な役割を果たしている。
活動を更に発展させていくために、活動に賛同する教員をさらに増やし、食・医療・福祉・健康・教育に関係する専門の知識を駆使して、安心して子育てができるよう取り組んでいる。
ボランティア・市民活動支援センターでは、学生が積極的にボランティア・市民活動に参加することによって、実社会と接点を持ち、学問の深化、市民意識の醸成、他者への理解を図ることができ、効果的な教育活動を推進していくことが可能となっている。これらのボランティア・市民活動の経験については、「ボランティア・市民活動論」における実践レポートとしてまとめることを通じて、教育活動の推進に役立っている。更に、ボランティア・市民活動をとおしての主体性の確立と、対人との係わりの中で培う豊かな経験によって、病院実習、施設実習、教育実習等に参加する際の実習前教育・就職活動等において大きな教育的効果があると考える。ボランティア・市民活動は、専門性の事前学習のみならず、学生として社会にチャレンジし、社会のニーズを把握するため、学生が地域と共に学び育つ有意義な教育となっている。
それぞれ学生の学びに好影響を及ぼしており、学生の就職活動その他結果に表れている。

関連サイトのURL
- 子ども・家族支援センター公式HP
- https://www.takasaki-u.ac.jp/contribution/family-support
- ボランティア・市民活動支援センター公式HP
- https://www.takasaki-u.ac.jp/contribution/volunteer
- ボランティア・市民活動支援センター公式ブログページ
- https://blog.takasaki-u.ac.jp/center-blog/volunteer