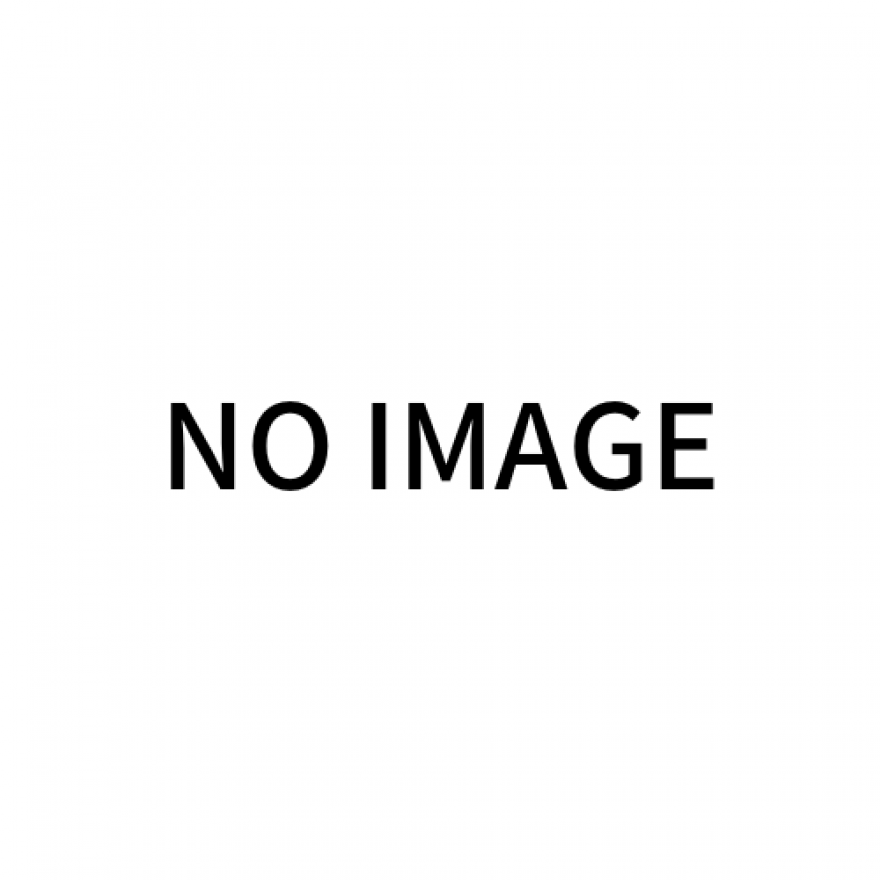基準9:社会連携・社会貢献
大学の特性を生かした研究成果の還元
取組み事例
産学官連携を通じて研究成果を社会に還元するべく、「知財事業推進センター」を設立し、教職員による知的財産の創出及び特許出願の学内啓発、製品の販売に向けた支援を継続的に行っており、実際に医療機器メーカーとの共同開発から製品の販売に至っている。また、教育、医療、研究の面から、SDGsの達成に向けて取り組むため、これに関するフォーラムや基礎講座の開催などの積極的な活動を行っており、川崎市の「かわさきSDGsゴールドパートナー」にも認定されている。このように、大学の特性を生かして地域連携・産学官連携の体制を強化し、地域における医療機関及び教育研究機関として重要な役割を果たすことが期待できる取り組みとして評価できる。
ここがポイント
- 「知財事業推進センター」を中心に教職員による知的財産の創出及び特許出願の学内啓発、製品の販売に向けた支援を継続的に行っている。
- 教育、医療、研究の面から、SDGsの達成に向けて積極的にフォーラム等を開催している。
大学からのコメント
産官学連携を通じて研究成果を社会に還元することについては、「知財事業推進センター」により教職員による知的財産の創出及び特許出願の学内啓発、製品の販売に向けた支援を継続的に行っている。遊道和雄大学院教授のチームが、神奈川県水産技術センター、国立研究開発法人水産研究・教育機構と共同で進めているマグロ喫食試験による抗酸化剤「セレノネイン」の研究において、生活習慣病改善や老化予防に寄与する可能性があるとの成果が出たことを受け、全国有数のマグロ水揚量を誇る神奈川県三浦市では、三浦市商工会議所が「まぐろ未病改善効果研究会」を発足させた。本学でも引続き「三崎マグロ」を通じた『食と未病に対する研究』をしている。
教育、医療、研究の面からのSDGsについては、2023(令和5)年12月27日付で神奈川県より「かながわSDGsパートナー」として登録された。
SDGsの取組については、2023(令和5)年7月にはSDGs専用のホームページを開設し、医療系単科大学の強みを活かし、「教育」「医療」「研究」に加え、「地域社会貢献」「環境」の5テーマを重点課題として、SDGs目標達成を目指し、本学の取組を独自の2030年目標と合わせて、学内外に発信している。
1981年度から市民公開講座を開催し、高校生から高齢者までを対象に、身体のしくみ、病気の成り立ち、健康増進に関する情報を提供している。また2007年から川崎市教育委員会との連携事業として、地域住民対象に筋力アップ教室を開講し、2013年からは小学校高学年を中心に医療や健康に関心をもってもらうことを目的とした医療体験「メディカルキッズ」を開催するなど、これらの活動にも継続して取り組んでいる。