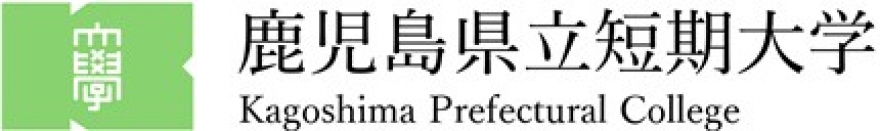基準9:社会連携・社会貢献
地域や産業界との多様な地域連携活動の展開~生涯学習と学生の地域連携の実践~
取組み事例
鹿児島県内唯一の公立短期大学として、多様な社会連携・社会貢献のチャンネルを持っており、長年にわたり奄美群島など離島でのサテライト講座を継続的に開講し、生涯学習・リカレント教育の機会を創出している。また、学生が近隣の地方公共団体のポスターの作成や茶産業が抱える課題をテーマとしたコンテストに参加するなど地域連携に取り組むなかで学びを実践することで、学習・研究へのモチベーションにつながっていることは評価できる。
ここがポイント
- 学びの場を広げる数多くの講座を開講することで、大学と住民がつながる機会を増やし、地域振興・活性化に貢献している。
- 地域連携への学生の参画は、カリキュラムだけではできない体験を通じて学生の学習に対するモチベーション向上という効果をあげている。
大学からのコメント
鹿児島県立短期大学の基本方針の5で、「県内唯一の公立短期大学として、県民の文化的かつ知的な生涯学習の一拠点を担い、地域や産業界との連携・協力を重視かつ拡充し、たえず地域の振興・活性化に貢献するよう努める」と定めています。
「ここがポイント」でも紹介されていますように、本学では「学びの場を広げる数多くの講座を開講」しています。第一に、公開講座です。本学3学科が、1年ごとに企画・講義を行っています。例えば令和6年度は生活科学科が「食と健康」というテーマで7回にわたって講義を行いました。申込者は100名を越えました。公開講座は、基本的には5月から6月にかけての土曜日の午後に開催されます。第二に、「金曜講演会」と題した本学附属図書館主催の講演会です。こちらは3週連続で金曜日の夜間に開催されるのが特徴です。テーマもさまざまですが、令和6年度はNHK大河ドラマに関連し、「源氏物語の世界」をテーマに講演を実施しました。第三は、奄美サテライト講座です。鹿児島には多くの離島があり、この講座では、奄美群島を1年ごとに、奄美大島→徳之島→沖永良部島→与論と回って実施しています。令和5年度は、奄美群島の日本復帰70周年にあたることから、金曜講演会と奄美サテライト講座の合同企画として、沖永良部会場、奄美会場、本学図書館会場をオンラインで結んで講演会を実施しました。また毎年、地域の公民館から依頼があり、本学の教員が講師をつとめる「生き生きシニア大学」も開催しています。水曜日の午後に、主にご退職されたシニアの方向けの講義を6回行っています。このように本学では、開催時期も、開催場所も、開催内容も多様な講座を準備しています。
さらに「ここがポイント」でも特記されていますように、地域連携へ学生も参画しています。デザインを学ぶ生活科学専攻の学生が、地方公共団体が発行する広報紙の①表紙デザイン、②特集ページの企画&デザイン、③コーナーページのデザインリニューアル、などを担当しました。特集ページでは当該地方公共団体をPRするポスターを制作しましたが、非常に好評でした。商経学科のゼミの活動として鹿児島茶のPR策をまとめたものが、「日経STOCKリーグ」のルーキー賞を受賞しました。大学生部門での入賞は鹿児島県内初となります。この他にも鹿児島市役所との連携協定事業も行い、学生が地域と連携する機会も提供しています。
関連サイトのURL
- 本学学生がプロデュースした地方公共団体の広報紙のページ
- https://www.city.makurazaki.lg.jp/site/koho/25470.html
- 日経ストックリーグの結果ページ
- https://manabow.com/sl/result/24/